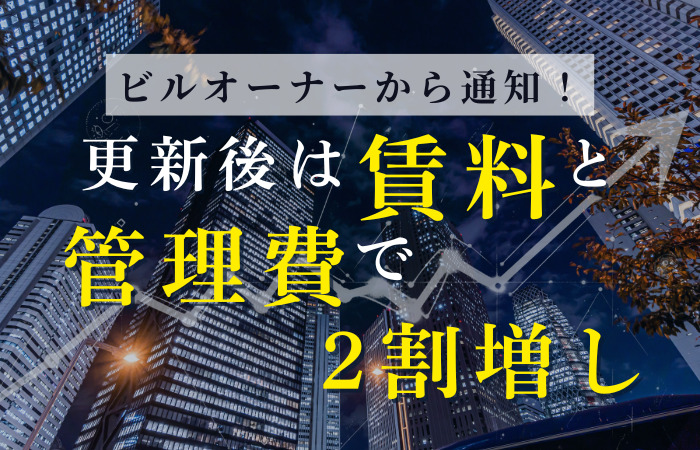
大都市の中心部では、更新時の値上げ要求が頻繁に行われています。
これは、世界の投資マネーが日本の大都市の家賃が安く、円安により物件評価の割安感があるためです。
米英欧では定期建物賃貸借契約が一般的です。日本の更新のある「普通賃貸借契約」は、世界の都市ではあまり見かけません。賃料には、新規賃料と継続賃料があります。普通賃貸借契約は、賃貸人(以下、ビルオーナー)から賃借人(以下、テナント)への更新拒否はできません。定期建物賃貸借契約(以下、定借)では、リース期間中は賃料の増減額は原則できません。
また、普通賃貸借契約の更新協議においてトラブルになった場合、調停前置となります。これは裁判所で、裁判官および賃貸借の専門家がビルオーナー、テナントの主張を聞き、中立的立場で合意を促す民主的な仕組みです。
ビルオーナーの腹読みで落とし所が決まる
ビルオーナーから家賃の増額通知!目的はなに?
- 収益還元、利回りを適正にして資産価値を上げ、売却を考慮
- 建物のグレードアップにより、テナントから選ばれる賃貸物件に改修
- 普通賃貸借契約のスタイルを国際的スタンダードな定借に変更するため(定借にしていただけるなら、今回の値上げは据え置きにしましょう)
- 近隣物件と比べて家賃が安い
- テナントの業績が悪く破産リスクが高い。マナーが悪く、他のテナントから苦情がくる悪質なテナント(退去してほしいテナント:貸金業、風俗など)
- 近隣で大規模開発があり、地価の上昇が予想される(売却および建て替えを検討)
- ①〜⑦の複合的理由
上記①〜⑦に詳しい専門家(不動産インテリジェンス)に相談するのが上策です。
「失われた30年—世界から見たら給料も上がらず、家賃も管理費も上がらず」
未来はインフレに突入し、金利のある社会に向かっています。給料も二極化、不動産も家賃も二極化していきます。
裁判所より調停前置の呼び出し…拒否できる?
ビルオーナーは不動産に関する知識も経験もあります。近年は不動産投資法人も多くなっており、株主が外資の場合、訴訟は頻繁にあります。
日本人特有の「誠意」では物事は解決しません。
合理的なビルオーナーは適正賃料を費用ゼロで知る方法として、調停前置の申立てをするケースが増えています。これは、裁判所に継続賃料を査定する専門家がいるためです。普通賃貸借契約(合意済み)から新規賃料との二分の一の適正賃料を知るための手続きと割り切り、法律の目をかいくぐる強者も昨今は多くなりました。本当のプロは、2〜3回の面談で上記を見抜きます。その次は調停前置を拒否します。
ペナルティーはありません。
ビルオーナーの目論見が外れて訴訟になれば、適正賃料鑑定書の費用負担、訴訟の立証責任はビルオーナーにあります。適正賃料の査定書(鑑定書)、弁護士費用、すべてビルオーナー負担となります。高額な費用となります。
もう一つ重要なポイントは、家賃だけで争うと不利になるということです。共益費・管理費・敷金償却費、すべてを実質家賃として裁判で決着を目指すことです。不動産インテリジェンスは、現役の専門家が強いです。
家賃増額 5%以上の増額は拒否!退去を念頭に協議する
不動産の地価上昇率はデータが公表されており、上昇率は家賃の増減額の明確な基準となります。大都市の中心部でも、裏道一本入るだけで家賃は大きく違います。
退去を念頭に協議してください。
原状回復義務履行、敷金返還まで責任を持って相談できる専門家に依頼してください。移転先のデザイン&ビルド、すべて真摯に相談に乗ってくれます。
以下は一般的な、家賃の増減額の解説です。弁護士の費用についても、参考程度に書いてあります。
賃貸オフィスや店舗の更新時に賃料を値上げ要求!交渉できるか?
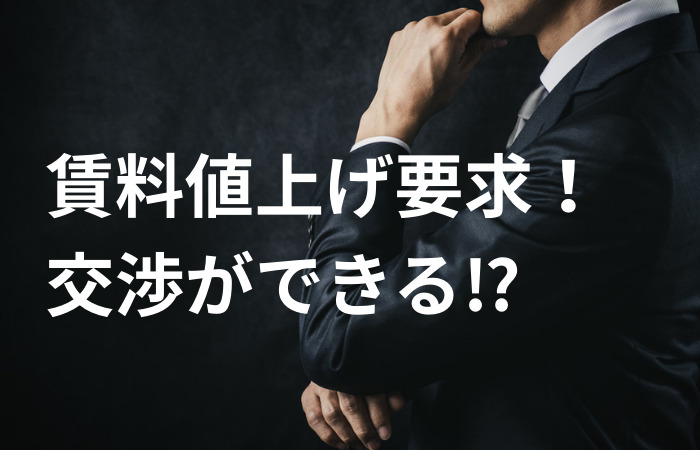
賃貸オフィスや店舗の更新時に賃料値上げが通知されることは多くのテナントにとって重大な問題です。昨今では、特に都市部を中心に地価や市場価格が上昇し、それに伴ってオーナー側から賃料の値上げが求められるケースが増えています。また、物価高騰による管理費や設備維持費の増加も背景にあり、オーナー側にも一定の理由があります。しかし、テナントにとって賃料負担の増加は経営を圧迫し、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。対策は、賃料増減額の専門知識が必要となります。
賃料更新時の値上げの実態
賃貸オフィスや店舗の賃料更新時の値上げ幅は一般的に5%〜10%程度とされていますが、市場の状況や地域によってはさらに大きくなる場合もあります。普通賃貸借契約では、更新の権利があるため比較的交渉の余地が広く、一定の譲歩を見せることが多いです。一方、定期建物賃貸借契約では更新権がないため、交渉はやや難航しやすく、値上げを受け入れざるを得ない状況となります。オーナーが値上げを求める理由としては、近隣芒種の物件と比較して、家賃が不適切、公租公課の変動、建物設備の省エネ、安全対策の管理費の上昇などが挙げられます。特に建物の経年劣化や共用部分の修繕、設備の更新費用などは、値上げの正当な理由としてオーナー側から提示されることが多いです。
交渉が可能な根拠と交渉のポイント
賃貸オフィスや店舗の賃料交渉には法律的な根拠があります。借地借家法に基づく賃料増減請求権があり、市場相場と比較して妥当でない場合、テナント側から賃料の見直しを要求できます。具体的には周辺物件の市場相場を調査し、自分の借りている物件が相場より高い場合は、それを根拠に交渉することが効果的です。
また、交渉時にはテナントとしての信用性や長期入居の実績をアピールすることも有効です。オーナーにとってテナントの入れ替えは空室期間や広告費用などのコスト負担が大きいため、安定して長期間入居しているテナントに対しては譲歩の余地が生じやすいです。
交渉を成功させるためには、賃料そのもの以外にも条件面で妥協点を見つけることがポイントです。具体的には、契約期間の延長を提案し、その代わりに賃料の上げ幅を抑える方法や、共益費や管理費の見直し、設備やサービスの改善をオーナー側に求めるといった方法があります。これら代替案を提示することで、双方が納得できる交渉結果を導きやすくなります。
1. 市場相場を調べる(専門家に簡易査定依頼)
- 近隣の類似物件の賃料と比較して、現在の家賃が妥当かどうかを確認。
- 賃料が相場より高い場合、それを根拠に交渉可能。(賃料は増減額ともに協議可能)
2. 協議の重要事項
- 普通賃貸借契約から定期建物賃貸借契約に変更する。
- 安定したテナントであることをアピール。
- 移転するとオーナーも新しいテナント探しのコストがかかるため、値上げを抑える理由になる。
- 賃料は少し上がるが、共益費を下げるなどの交渉。(実質賃料を基準に協議)
3. 設備・サービスの改善を要求
- 賃料アップに見合う設備改善(エアコン、セキュリティ、共用スペースの充実など)を求める。
4. 退去の可能性を示唆
- 「他の物件も検討している」と伝えることで、オーナー側が値上げを再考する可能性あり。
5. 賃貸借の専門家や弁護士に相談
- 継続賃料協議は、専門家でもきびしいです。
オーナー側も空室リスクを避けたいので、合理的な理由を示せば交渉は可能です。まずは話し合ってみましょう。
賃料交渉が難航した場合の対応

賃料交渉が難航した場合、最終的には訴訟に発展するケースもあります。訴訟の流れとしては、まず弁護士を通じて正式な増減請求を行い、調停を経て合意に至らなければ裁判に移行します。訴訟では、弁護士費用として着手金が30万円前後、報酬金が経済的利益の10%〜18%程度かかるのが一般的です。 ここでの「経済的利益」とは、賃料の増減幅に契約期間や影響年数(通常2〜7年)を掛けて算出するものです。普通賃貸借契約は、7年の経済的利益に弁護士の成功報酬率をかけて算出します。定期建物賃貸借契約では、契約期間満了までの経済的利益が基準となります。貸主、借主ともに増減額は不可能と思われます。
※経済的利益は、弁護士費用(特に報酬金)を決める際の基準として使われます。
賃料交渉で訴訟する場合の弁護士料は?
賃貸オフィスの賃料交渉が訴訟に発展した場合、弁護士費用は以下のように構成されます。
着手金
-
- 交渉段階:一般的に30万円(税込33万円)程度から。
- 訴訟段階:交渉から訴訟へ移行する場合、追加で10万円(税込11万円)程度が加算されることがあります。
報酬金※極めて高額になる普通賃貸借契約
-
- 経済的利益(賃料増減額の差額×7年分)に応じて、以下の割合で算定されます。
- 300万円以下:17.6%~
- 300万円~3000万円:11%~17.6%
- 3000万円以上:3.3%~11%
- 経済的利益(賃料増減額の差額×7年分)に応じて、以下の割合で算定されます。
実費
-
- 裁判所への提出書類作成費用や交通費などが別途必要となります。
これらの費用は、依頼する弁護士事務所や案件の複雑さによって異なる場合があります。具体的な費用については、弁護士事務所に相談し、詳細な見積もりを取得することをおすすめします。
最後に
賃料や管理費の増額通知を受けた際、テナントにとっては大きな負担となりますが、オーナー側にも合理的な背景があります。重要なのは、感情的にならず、法的根拠や市場相場をふまえた冷静な交渉姿勢です。場合によっては専門家の知見を借りることで、賃料や条件面での譲歩を引き出すことが可能になります。テナントとしての信用性や長期入居の実績を活かしつつ、最善の選択をすることが、今後の事業継続において鍵となります。
店舗・オフィスの移転に伴う原状回復や敷金返還についても、適正な査定と無料相談を承っております。さらに、新店舗出店やオフィスの新設など、ビジネスの成長を見据えたワンストップ支援も行っております。働きやすく生産性の高い環境づくりを、ぜひご一緒に実現しましょう。最後までお読みいただき、ありがとうございました。貴店および貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。
|
|
萩原 大巳 (Hiromi Hagiwara)
一般社団法人RCAA協会 理事
オフィス移転アドバイザーとしての実績は、600社を超える。原状回復・B工事の問題点を日経セミナーで講演をする。日々、オフィス・店舗統廃合の相談を受けている。オフィス移転業界では、「ミスター原状回復」と呼ばれている。 |
|---|




