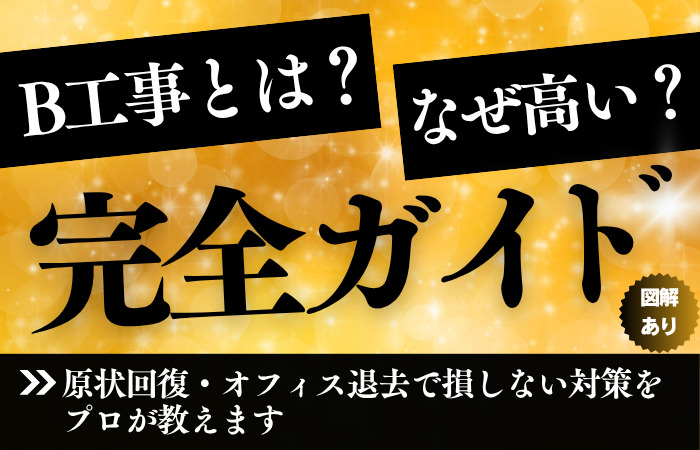
はじめに
「B工事ってなぜこんなに高いの?」「C工事と何が違うの?」
オフィスや店舗の入居・退去に関わる“B工事”ですが、その仕組みや費用構造を理解せずに進めると、想定外の出費やトラブルに発展しかねません。
この記事では、B工事の基礎知識、発生の仕組み、費用が高くなる理由、C工事との違い、そしてトラブルを避ける方法までを徹底解説します。
B工事とは?【基本を3分で理解】
オフィスや店舗での工事は「A工事・B工事・C工事」の3区分に分けられます。
| 区分 | 発注者 | 費用負担 | 工事業者 |
|---|---|---|---|
| A工事 | ビルオーナー | ビルオーナー | ビル指定業者 |
| B工事 | テナント(借主) | テナント | ビル指定業者 |
| C工事 | テナント | テナント | テナント指定業者 |
B工事とは、テナントが費用を負担するが、施工業者はビルオーナー側が指定する工事のこと。たとえば、空調の増設や照明変更、電気設備の接続などが該当します。
なぜB工事が発生するのか?
B工事は、テナントの要望により既存のビル設備に手を加える必要がある場合に発生します。これらの工事は、建物全体のインフラに直結するため、施工ミスや仕様違反が他のテナントや共用設備に重大な影響を及ぼす可能性があります。そのため、ビルオーナーや管理会社が責任を持って指定業者に施工させるB工事として扱われます。
標準仕様の設備に手を加えると、ビル全体の構造や安全性に関わるため、B工事としてビル指定業者により施工されます。
例)
- 空調機器の増設 → ビルの空調系統と連動する
- 電気容量の増強 → ビルの幹線電源に接続する
B工事が高額になる3つの理由

B工事の費用が高額になる背景には、構造的な問題と実務的な制約が複数存在します。以下の3点が主な理由として挙げられます。
- 指定業者による単一見積(相見積不可):B工事はビルオーナーや管理会社が指定した業者しか使えないため、相見積もりができず価格競争が働きにくい構造になっています。そのため、費用が市場相場より割高になることがよくあります。
- 複雑な工程・短工期での施工(調整コスト増):オフィスや店舗の入居スケジュールに合わせてタイトな工期が求められる中、B工事はC工事との工程調整が必要になります。短期間で正確な施工を求められる分、人件費や工程管理のコストが高くなります。
- 高い技術力・安全基準が求められる(特にビル中心部への介入):B工事ではビル共用設備や躯体に関わる作業が多く、専門技術や高度な安全対策が必要になります。そのため、一般的な内装工事よりも施工難度が高く、コストがかさみやすくなります。
また、原状回復時にもB工事が必要となることがあるため、入居時・退去時の両方でコストが発生します。
C工事が決まらないとB工事も決まらない?
はい、本当です。C工事(内装レイアウトや照明プラン)に応じて、B工事の範囲が変動するからです。
例)
- 会議室増設 → 空調分岐(B工事)
- 電源機器増設 → 電気容量アップ(B工事)
C工事の内容次第でB工事が変わるので、設計初期の段階からB工事に関係する部分を洗い出すことが重要です。
B工事を減らす方法は?
B工事の費用を抑えるには、そもそも「B工事が発生しにくい設計や進め方」を意識することが重要です。以下のような工夫を行うことで、不要なB工事を減らし、C工事で完結できるケースを増やすことが可能になります。
- C工事設計でビル設備に干渉しないよう工夫する:空調・電源・消防設備などの既存設備に手を加えないレイアウトにすることで、B工事の必要性を下げられます。
- 早期にビル管理会社と設備接続ポイントを協議する:初期設計段階でビル側と協議を行い、B工事がどの範囲で必要かを事前に明確にしておくことで、不要な設計変更を防げます。
- 専門家(工事管理者やコンサル)に事前相談する:原状回復や内装設計に精通した専門家に早めに相談することで、コスト抑制と設計合理化が可能になります。
B工事を知らずに契約すると?
B工事に関する理解や確認を怠ったまま契約を進めてしまうと、後から想定外の費用が発生したり、工期が大幅に遅れたりするなど、トラブルにつながるリスクがあります。特に契約書に工事区分や費用負担の明記がない場合、責任の所在が曖昧になり、法的な紛争に発展するケースも少なくありません。
- 工事費が2〜3倍に増加
- 工期が伸びて入居が遅延
- 退去時もB工事で原状回復が必要に
- 契約書に工事区分がないと、法的トラブルに発展する可能性も
契約前にB工事の範囲・費用負担を必ず確認しましょう。
事前確認チェックリスト(契約・設計前に)

- 工事区分表があるか?
- 入居前の原状図面は取得済みか?
- 工事負担区分(B/C工事)は契約書に明記されているか?
- 設計上ビル設備に干渉していないか?
- ビルオーナーや管理会社との協議記録が残っているか?
- 見積りの内訳にB工事項目が明示されているか?
- 退去時の原状回復に関してB工事が必要か確認しているか?
- C工事の設計段階で、B工事への影響を検討しているか?
- 工事内容に応じた工期・工程調整がなされているか?
よくある質問(FAQ)
Q:B工事の費用は安くできる?
→ 完全には難しいですが、C工事への変更相談や仕様簡素化で費用圧縮の余地があります。
Q:B工事で設置した設備の所有権は誰にあるの?
→ 民法上は、建物に恒久的に固定された設備はビルオーナーの所有物になります。一方で、テナントが費用を負担しているため、会計上はテナントの資産とされ、償却の対象となります。
| 観点 | 所有者 | 説明 |
|---|---|---|
| 民法上の所有権 | ビルオーナー | B工事で建物に恒久的に取り付けられた設備(例:天井配線、空調機など)は「建物の一部」とみなされるため、所有権はビルに帰属します。 |
| 会計上の資産区分 | テナント | テナントが費用を負担した設備は「借主の資産」として計上され、減価償却や償却資産税の課税対象になります。 |
Q:B工事でよくあるトラブルは?
→ B工事では、以下のような具体的なトラブルがよく発生します:
- 見積額が想定より大幅に高い:オーナー指定業者のみで相見積もりができず、費用が割高になるケースがあります。
- 契約書に工事区分の記載がなくトラブルに:B工事かC工事かが不明瞭なまま契約し、どちらが費用を負担するかで揉めることがあります。
- 工期遅延により入居・開業が遅れる:B工事の発注が遅れ、内装全体のスケジュールに影響するケース。
- 施工内容が曖昧なまま進行し、品質に問題が出る:設計時の確認不足により、完成後に設備トラブルや追加工事が発生することがあります。
まとめ|B工事を制す者がコスト管理を制す
- B工事の仕組みを理解すれば、コストとトラブルの回避が可能
- 見積チェックや設計段階からの戦略が重要
- 専門家の活用でリスク最小化を図ろう
無料相談のご案内
B工事や原状回復に関するお悩みは、RCAA協会までご相談ください。
|
|
萩原 大巳 (Hiromi Hagiwara)
一般社団法人RCAA協会 理事
オフィス移転アドバイザーとしての実績は、600社を超える。原状回復・B工事の問題点を日経セミナーで講演をする。日々、オフィス・店舗統廃合の相談を受けている。オフィス移転業界では、「ミスター原状回復」と呼ばれている。 |
|---|



